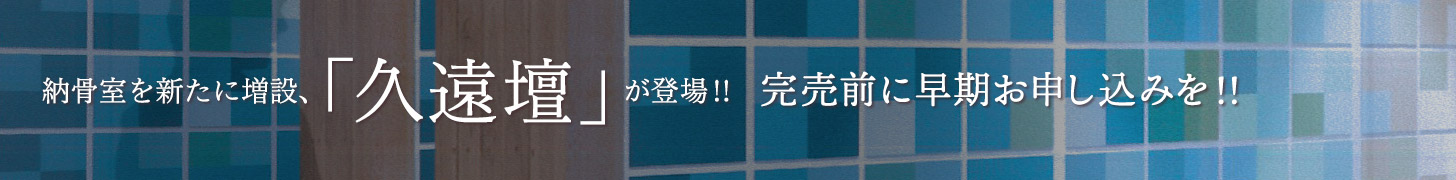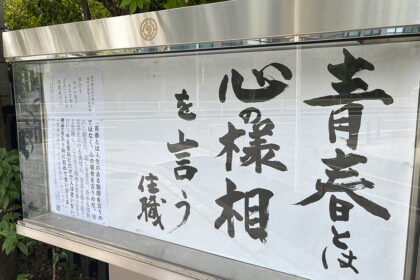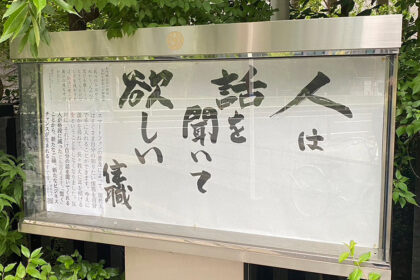「齢〔よわい〕はや 米寿むかえし としのくれ」
上の一句は、佛立第十八世講有日地上人御後室・宣子大奥様が米寿をお迎えの折にお詠みになった一句です。その際に大奥様は、「いつの間にか、この世に生を受け八十八年も経ってしまい、皆様から米寿、米寿とお祝いの言葉をいただき、戸惑っております。ありがとうございます」と述べられ、私どもにいろいろと教えてくださいました。そのお話をお伝えさせていただきます。
大奥様は、佛立第十五世講有日晨上人のご息女として、当時の麻布櫻田町にあった乗泉寺にてお生まれになり、清風寺にお輿入れになる前までを東京でお過ごしになりました。その間に就職、戦争、疎開、終戦を経験されたお話もしてくださいました。当時の世情を知ることのできる大変貴重なお話ばかりです。
そして終戦後、復員して間もない日地上人とのご縁談が進み、本山宥清寺本堂にて結婚式が執り行われました。そうして大奥様は清風寺でご奉公されるようになったわけです。昔の清風寺は今の裏側に正門があったこと、現在のような大通りはなく幅五メートルほどの川が流れていたこと、ジェーン台風(昭和25年9月)の後、建立された本堂が斬新な寺院建築で珍しく一般の新聞にも大々的に報道され本願寺や南御堂も、この新しい清風寺をモデルに建てられたことなど、私たちの知らないことをたくさん教えていただきました。その本堂も含め、大奥様は計4回もの開筵式をお迎えになり今日に至っておられます。その中でたくさんの子や孫、曾孫に囲まれて、清風寺の法灯を繋ぎ護られてきたのです。
八十八歳のお祝いをさせていただいてから早12年、大奥様は昨年12月28日に満百歳のお誕生日をお迎えになりました。「百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)」のお祝いを日地上人の御弟子である御導師方やそのご家族、清風寺教務寺族一同で心を込めてさせていただきました。朝参詣の本堂で大奥様のお元気なお姿を拝見するだけで、私ども清風寺教講一同は御礼感謝の気持ちでいっぱいです。こちらの都合ばかりになりますが、どうか大奥様にはこれからもお元気なお姿で、私たちにお折伏をいただきたいと願うばかりです。大奥様、まことにおめでとうございます。